施工管理の仕事に携わる方々にとって、残業が多いというのは避けられない問題と感じている方も多いでしょう。工事が始まる前から終わるまで、連日長時間労働が続くことも少なくありません。では、なぜ施工管理の残業はこれほど多いのでしょうか?本記事では、施工管理の残業の実態や、その原因、対策について詳しく解説していきます。また、残業のメリットやデメリット、残業を減らすための具体的な企業の取り組みや個人の対応方法についても見ていきます。読者の皆様が、より健全な働き方を実現できるよう役立つ情報を提供したいと考えています。
施工管理の仕事内容
まずは施工管理の仕事内容を確認しましょう。施工管理は以下の4つの主要な管理業務を担当します。
- 工程管理:工事を計画通りに進めるための管理です。作業の進捗を常に把握し、予定通り進むよう調整します。
- 原価管理:予算内で工事を完了させるために、材料費や人件費などの費用を管理します。
- 品質管理:求められる品質を確保するため、工事の内容や完成度をチェックします。
- 安全管理:労働災害を防ぐために、安全に工事を進めるための対策や教育を実施します。
施工管理は現場の状況を把握しつつ、多くの業者や職人とやり取りし、作業全体を管理します。これらの業務は一つ一つが重要であり、人命に関わる責任が大きいため、慎重に遂行する必要があります。その結果、業務量が増加し、長時間労働につながりがちです。
加えて、施工管理では多岐にわたる業務を同時並行で進めることが多く、優先順位を付けて処理するスキルが必要です。しかし、現場ごとに状況が異なるため、柔軟な対応力も求められます。このような点からも、施工管理の労働時間が長くなりがちであることがわかります。
関連記事:施工管理の仕事内容を徹底解説
施工管理の残業が多い理由
施工管理の残業が多いのには様々な理由があります。
- 仕事量が多い:施工管理には、多数の管理業務と多岐にわたる責任が含まれています。各業務が互いに関連し合っているため、一つの業務が遅れると他の業務にも影響が出て、結果として全体の作業量が増えてしまうことがあります。
- 事務作業が現場終了後に発生する:施工管理者は、現場での業務に加えて大量の事務作業も抱えています。これには、進捗報告書の作成や、原価管理のための記録整理、品質管理のための各種チェックリストの確認などがあります。これらの作業は現場業務が終了した後に行われることが多いため、残業が増える要因となります。
- 工程管理に時間がかかる:工程管理は工事全体の進行をスムーズに行うための重要な業務です。しかし、予期しない天候不良や資材の遅延などが発生した場合、工程を再調整する必要があり、これが残業の原因になります。工程の遅れを最小限にするために、計画の見直しや関係者との調整に多くの時間を費やすことになります。
- 安全管理を徹底する必要がある:施工管理の安全管理は非常に重要であり、事故が起きないよう徹底した対策が求められます。そのため、現場の巡回や安全確認に多くの時間を費やすことがあり、これも残業が増える理由です。
責任が大きい仕事が多く、何度も確認が必要なため、結果として労務量が増えてしまいます。これらの要因が施工管理の残業の多さに直結しています。
おすすめの記事:施工管理の「つらい」「きつい」「大変」
施工管理の残業時間の実態と平均
施工管理の現場では、残業はほぼ避けられない状況です。業務の性質上、プロジェクトの進捗管理や各種トラブルへの対応、さらには関係者間の調整などがあり、どうしても勤務時間が長引くことが多くなります。本節では、施工管理職の残業の実態と、具体的な平均残業時間について詳しく見ていきます。
平均残業時間はどれくらい?
施工管理職の平均的な残業時間は、月に40時間から80時間程度と言われています。特に繁忙期にはこれを超えることも珍しくなく、過労死ラインとされる月80時間を超えるケースもあります。
また、現場の規模や工期によっては、100時間を超えることもあります。繁忙期や大型プロジェクトの場合、休日出勤が増えることもあり、全体の労働時間がさらに長くなります。このように、施工管理の労働時間は非常に長くなりがちであり、家族やプライベートの時間を犠牲にすることが多いというのが実情です。
他業種と比較して
他業種と比べても、施工管理の残業時間は非常に多いとされています。特に建設業界では、慢性的な人手不足もあり、一人当たりの業務量が増えやすい環境が残業時間の増加に拍車をかけています。また、工期が厳格に設定されていることが多く、遅延を避けるために労働時間が長くなることがよくあります。他の業界と比較しても、こうした外的なプレッシャーが残業の多さにつながっていることがわかります。
施工管理残業あるある
施工管理職の残業には、特有の「あるある」が存在します。これは多くの施工管理者が共感できる部分であり、共通の経験と言えるでしょう。本節では、施工管理の現場でよく見られる残業の原因や状況を具体的に挙げていきます。
残業が多くなる理由は、施工管理者に共通している部分が多いです。ここでは、よく見られる残業の原因を紹介します。
機器の納期が遅れて工期に間に合わない
工事にはトラブルがつきものです。機器や材料の納期遅れによって工事が遅れることがありますが、顧客から工期の延長を許可されることは難しいため、遅れを取り戻すために残業が増える傾向があります。また、資材の不足や誤配送なども工事の進行に影響を与えるため、柔軟に対応しながら作業を進める必要があります。
労災事故で工事が一時停止する
労災事故が発生した場合、大小問わず現場検証や緊急の安全教育が必要となり、工事が一時停止します。私自身、骨折や裂傷といった大きな事故を経験し、約1ヶ月の休工を余儀なくされたことがあります。安全教育の期間中は書類作成に追われ、その後の工事は遅れを取り戻すためにさらに残業を行いました。労災が発生すると、現場の安全確保を最優先にしなければならないため、他の業務も滞りがちになり、これが残業につながります。
おすすめの記事:施工管理のケガを解説
事務処理を一人で抱え込み仕事が終わらない
施工管理の仕事には多くの事務作業が伴います。人手不足の場合、事務担当者からの応援が得られず、全ての作業を一人で行う必要があり、その結果、深夜や休日に書類作成をすることになります。限界を感じたらすぐに応援を呼ぶことが大切です。事務作業が滞ると、現場での管理作業にも影響が出るため、結果として残業が長引くことになります。
年間360時間を超えないギリギリまで残業をして、それ以上はサービス残業になる
休日や深夜の作業で年間の残業が360時間に達することがありますが、これ以上は会社が認めてくれないため、超過分はサービス残業になりがちです。サービス残業を避けるため、必要であれば転職を検討することも一つの手段です。特に、会社によってはサービス残業が常態化していることがあり、こうした状況が精神的な負担をさらに増やします。
残業のメリット
残業というとネガティブな面が強調されがちですが、一方で施工管理者にとってメリットもあります。もちろん健康を害さない範囲での残業ではありますが、経験を積むことや収入の面でのプラス効果も期待できます。本節では、残業が持つ可能性のあるプラス面について触れていきます。
残業にはデメリットばかりではなく、いくつかのメリットも存在します。異業種に転職する際には、これらのメリットをどう捉えるかが重要です。
- 残業代で給料が増える:残業代が加算されることで、手取りの収入が増えるため、特に若い施工管理者にとっては収入を増やすチャンスとも言えます。
- 長時間働くことで経験と実力がつく:多くの現場経験を積むことで、トラブル対応力や管理スキルが向上します。こうした経験は施工管理者としてのキャリアを積む上で非常に重要です。
- 同僚とのチームワークが深まる:長時間の現場作業を共にすることで、同僚との連携や信頼関係が強化されます。厳しい状況を乗り越えることで得られるチームワークの強さは、今後のプロジェクトでも大きな武器になります。
ただし、これらのメリットを享受するには、健康管理や適切な休息を確保することが不可欠です。無理をしすぎると、体調を崩したり、精神的に疲弊することになりかねません。
おすすめ記事:施工管理の年収は高い
過労による健康リスクとその対策
残業が続くと、どうしても健康リスクが高まります。特に施工管理のように重責を負う仕事の場合、心身ともに負担が大きくなりやすいです。この節では、過労による具体的な健康リスクと、それに対処するための方策について詳しく説明します。
健康リスク
長時間労働は、心身にさまざまな悪影響を及ぼします。
- 過労死のリスク:長時間労働を続けることで、心筋梗塞や脳卒中などのリスクが高まります。
- うつ病などのメンタルヘルス不調:精神的なストレスが蓄積すると、うつ病や適応障害といったメンタルヘルスの問題を引き起こすことがあります。
- 生活習慣病のリスク増加:運動不足や不規則な生活習慣が続くと、高血圧や糖尿病といった生活習慣病のリスクが増加します。
健康管理の重要性
健康を維持するためには、適切な労働時間と十分な休息が不可欠です。定期的な健康診断やストレスチェックを活用し、自身の体調を把握することが大切です。また、リフレッシュするために趣味の時間を作ることも有効です。体力づくりやリラクゼーションを取り入れることで、仕事の効率も向上します。
労働基準法に基づく残業規制
残業を行うにあたっては、法律に基づいたルールを守る必要があります。日本の労働基準法では、残業時間には明確な上限が定められており、これを超える労働は許されていません。この節では、施工管理における残業の法律的な側面と、規制の内容について詳しく見ていきます。
法定労働時間
日本の労働基準法では、1日の労働時間は8時間、週40時間と定められています。
残業時間の上限
2019年の労働基準法改正により、残業時間は月45時間、年360時間が原則となりました。特別条項を結ぶことで一時的に上限を超えることが可能ですが、年間720時間を超えてはならないと定められています。こうした法的な制約があるにもかかわらず、現実にはそれを超える労働が常態化している場合もあり、問題視されています。
違反時の罰則
法定を超える残業が常態化している企業は、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。改善されない場合、罰金や企業名の公表などの罰則が科せられることもあります。労働環境の改善は企業の責任でもあるため、従業員が安心して働ける環境を提供することが求められています。
残業を減らすための企業の取り組み
施工管理の現場で残業を減らすためには、企業側の取り組みが非常に重要です。働き方改革や業務の効率化を進めることで、従業員の負担を減らすことが可能です。この節では、残業削減に向けた具体的な企業の取り組みと、それが施工管理に与える影響について説明します。
働き方改革の推進
近年、多くの企業が働き方改革を推進しています。業務効率化やIT化を進めることで、残業を減らそうとする動きが見られます。たとえば、クラウドベースのプロジェクト管理ツールを導入し、情報共有を迅速に行うことで業務効率が向上します。
人員の増強
施工管理の人手不足を解消するため、新規採用や中途採用を積極的に行い、人員を増強する企業も増えています。また、派遣社員や外部委託を活用し、特定の業務を分担することで、現場の施工管理者の負担を減らす取り組みも行われています。
業務プロセスの見直し
業務プロセスの無駄を省き、生産性を向上させるための取り組みも進んでいます。会議の短縮化やタスクの優先順位の見直しが行われています。特に、会議を短時間で効率的に行うことで、現場に戻る時間を増やし、残業を減らすことができます。また、事務作業をデジタル化し、書類の作成や提出をオンラインで行うことで、大幅な時間短縮が可能です。
残業が少ない企業の選び方とポイント
残業が少ない企業で働くことは、施工管理者にとって健康的で持続可能なキャリアを築くための重要な要素です。本節では、残業の少ない企業を選ぶためのポイントや、面接で確認すべき事項について詳しく解説していきます。
企業の労働環境を調べる
転職を考えている場合、口コミサイトや転職エージェントを利用して企業の実際の労働環境を調べましょう。社員の口コミや評価は、実際の労働時間や企業文化を知る上で重要な情報源です。
働き方改革の取り組み状況
企業がどの程度働き方改革に取り組んでいるかを確認することも大切です。効率的な業務体制を整えている企業ほど残業は少ない傾向があります。たとえば、フレックスタイム制の導入やリモートワークの推奨など、柔軟な働き方が可能な企業を選ぶことが、残業を減らすための一つのポイントです。
面接で質問する
面接時に残業時間や働き方について具体的に質問し、自分に合った企業かどうかを見極めましょう。具体的には、「平均的な残業時間はどれくらいですか?」や「働き方改革に対してどのような取り組みをしていますか?」など、残業に対する企業の考え方を把握することが大切です。
まとめ
施工管理の残業が多い理由とその対策について詳しく解説しました。業界特有の課題は多いですが、適切な対策を講じることで働き方の改善は可能です。個人と企業が協力し、健康的で持続可能な労働環境を作ることが大切です。自分の健康とキャリアを守るため、働き方を見直し、より良い職場環境を目指していきましょう。
特に、施工管理の仕事においては、一人で全てを抱え込むのではなく、周囲のサポートを得ながら働くことが重要です。業務効率を上げるためのスキルを磨き、会社全体で働きやすい環境を整えることで、残業を減らし、仕事の質を向上させることができます。
あなたの働き方を見直し、より良い職場環境を目指しましょう。


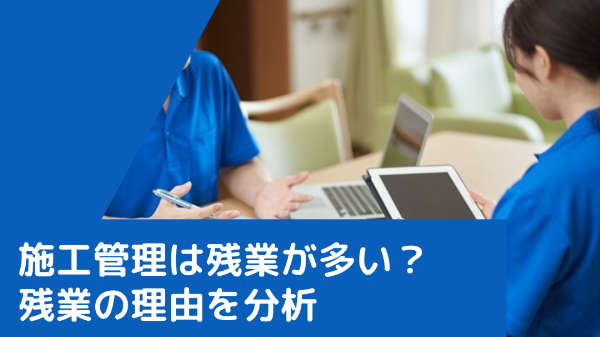
コメント